(POLYDOR 28MM 0461:LP:国内盤)
(SMCD 2/572524-2:CD)
「自分たちが好きな70年代のバンドみたいなことをしよう!」とスウェーデンの地方都市で試行錯誤した結果、たまたま同じ時期に盛り上がっていたLA Metalと同じようなルックスになってしまった、とのメンバー談。裏ジャケットではタロットカードに見立てたメンバーショットがあるのですが、我がHasse Fは「The Lovers」だそうです。バラ持ってるぞ(笑)。音はメロデイアスなR n'Rという感じです。ガナリ気味のVo.の声は、伸びはいいのですがちょっと音痴気味です。
日本盤の解説は有島博志氏。それによると、1984年秋に220VOLTとBathoryと一緒にツアーを回ったらしいですが、あの故QuorthonのBathoryですか?まじですか?
(追記)このツアーの話はデマだとHasse本人に確認しました。こちらのインタビューをどうぞ。有島氏はどこでこんな話を掴まされたんでしょうね(^^;))
☆Spellbound / My Kinda Girl / Gone Rockin' (Sonet SON-2294:7inch) '84
リリース年がウソっぽいが、唯一の資料ではこうなっていた。「Rockin' Reckless」からの先行シングルだったのだろう。"My Kinda Girl "ドラムの音がダブダブで野暮ったいが、コーラスワークはとても美しいハードポップ。Def Leppard辺りを狙っていたのかな。B面はアルバム未収録曲。ミドルテンポのヘヴィロック。このバンドはメロディアスでもあるんだけど、それだけでは終わりたくない色々な試みをしていたと思う(実ったかどうかはともかく)。
☆Spellbound / Rockin' Reckless(Sonet SNTF-952:LP)'85
(SNTCD 952 / 527 526-2:CD)
プロデューサーはMotorhead等を手掛けたVic Maile。LPのインナースリーブにはメンバー達の幼児時代の写真も載っていまして、欧米人は赤ん坊でも彫りが深いんだなと妙に感心しました。弱みを握った感じです(謎)。
えーと、聞いた感想。1stに比べるとさらにR n' R寄りになった感じです。それをヘンしているのはキーボードやおかしなアレンジのおかげでしょう。キーボードの軽い音色は時代を考えると仕方がないとしても、挿入が唐突(汗)。Ola(ds)とAlf(g.key)のStrandberg兄弟の父親がSaxでゲスト参加(プロのJazzミュージシャンらしい)。歌にしても、リズムにしても、やりたいことが一杯で、でも若さ故に空振りしてる感じがかなりB級です。でも何か好き(^_^;)。よくオヤジ臭いとか暑苦しいと評されていたHasseのVo.は、1stより力みが抜けた感じだが、まだ成長過程の途中。力を抜いて歌う箇所はなんとなくPhilip Lewisっぽくて、全体としてGirlを彷彿させます(私にとってGirlは誉め言葉です)。しかしこのバンドには"Hollywood Tease"がなかった。あ、最後の曲はWhitesnakeのパクリだな。
あんまり良いこと言ってませんが、不思議と印象に残るメロディがあり、これは次のデモCDにも受け継がれています。
(追記)聞き慣れてくると"My Kinda Girl"ってすげーいい曲じゃないかと思えてきた。"Streetprowler"が愛おしいです。

Breaking The Spell
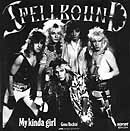
My Kinda Girl / Gone Rockin'
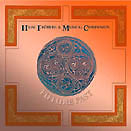 ついにHasse主導の作品も登場!本人的には「バンド」だそうです。リズム隊は元SpellboundのThomsson
(b.)とOla Strandberg (ds.)。Key.にはKjell Haraldsson (Michael Schenker
& friends, Glenn Hughes, HTP等のツアーメンバーを務めたことがある)を迎え、ギタリストは期待の新人Anton
Lindsjo:。「予想以上」とは違う、「予想外」の出来でした。
ついにHasse主導の作品も登場!本人的には「バンド」だそうです。リズム隊は元SpellboundのThomsson
(b.)とOla Strandberg (ds.)。Key.にはKjell Haraldsson (Michael Schenker
& friends, Glenn Hughes, HTP等のツアーメンバーを務めたことがある)を迎え、ギタリストは期待の新人Anton
Lindsjo:。「予想以上」とは違う、「予想外」の出来でした。