S(Z)amla mammas (z) Manna/Von Zamla
この人達のおかげで、脱線リスナー人生にとどめを刺されました。でも、幸せ。
えぇ、今更私が書くようなバンドではございません。プログレ雑誌だった頃のmarquee・50号の特集を読んでいただければOKです・・・・では作った意味がありません(^_^;)。拙い文ながら、よくS(Z)MMに使われる形容詞「ヴァイタルな」、を考えてみようと思います。
まず英和辞書で"vital"の意味を調べてみます。
- 生命の、命に関する、
- ・・・にとって絶対必要な、(to;for)
- 生き生きとした、活発な、
名詞にすると「生命維持に必須な諸器官」「急所」「核心部分」などがあります。(三省堂・グローバル英和辞典第3版)
生命といっても、生き方そのものになってしまうlifeや精神的なsoulと比べ、かなり肉体的な意味合いが強いと思います。おおよそS(z)MMに使われる「ヴァイタル」は3番目の「生き生きとした、生命感あふれる」にあてはまりますが、どうして力強い"powerful"ではダメなんでしょう?
私には学問的な解釈はできません。が、1998年の秋来日したエストニアのロックグループ、NE ZHDALIのライブで体験をすることができました。
公演最終日、吉祥寺・GOKサウンドで行われた公開録音は進行状況こそメチャ悪かったとはいえ、普段リスナーがCDでは感じることは難しい、ミュージシャンの反射神経の素晴らしさを目の当たりにすることができました。進行役の津山篤氏の指示で、どんどん膨らんでいくインプロビゼーション。日本の童謡さえ瞬時に吸収し反応する柔軟さ。頭で「このコードがこう来るから、ここでぶっ壊して」など考えてもいないでしょう。肉体が、音楽の波長に反応してるのだと思う。だからリスナーも頭で「これは脱構築だ、素晴らしい」と鑑賞・理解するよりも早く、体が反応してしまいます。それが人の心を揺るがさない訳がないのです。肉体に直結した音楽。
RIO発足後、世界中のアヴァンギャルドな(としか表現できない)バンドと交流を深めたFred FrithがSamla、特にドラマーのHasse
Bruniussonに強い影響を受けたそうです。もっともエッヂにいる音楽家が、何でそんなことを言うのだろうと思っていたのですが、なるほど、肉体的衝動さえ方法論として割り切っていた、様な気がする彼にとって、「こんなのありか」的な出会いだったに違いない。勿論スウェーデンの古都・ウプサラにこんな凄腕たちが居たのかと、唸らせるほどのテクだったというのは言うまでもないでしょう。(F
Frith「Gravity」のCDのライナーにその辺の話が載っているそうですが、私はまだ読んだことはありません。違ったらごめんなさいm(_
_)m)
破壊、ではなく「だってそーなっちゃったんだもん」的ノリ。5拍子、7拍子がきわめて普通なブルガリア舞踏音楽や「カルミナ・ブラーナ」の変態的譜割が、頭で理解しようとすると複雑怪奇になってしまうのに、歌ってみればごく自然、というアレ。NE
ZHDALIのライブで、以上のことを直観したのです。理屈は今、書いてる過程で付けてるものに過ぎません。
他に「ヴァイタル」が似合うバンドを探してみよう。初期BANCO、MAGMA、AREA、NU ・・・いかん、これ以上書くとキワモノだらけになってしまう(笑)。まぁ、この辺は好みもありますね。NUはともかく(^_^;)、民族色(=肉体的記憶。国籍が一致してるとは限らないし、民族ではなく個人体験と言うこともあるだろう)を織り交ぜてきわめて高度なテクニック、つまり出したい音はかなり忠実に再現できる能力を持っている人たちです。プレイヤー雑誌では表現手段にすぎない技術面に当然スポットをあてますが、やはり音楽を聴くだけならそこからもう一歩踏み込んだ、人の個性がもたらす特有のうねりやリズム感覚に心が向くことでしょう。人間が、その肉体を持って自分の音楽を演奏する。だからこそ「生命感」がある。ファッションやビジネスに血は通いませんし、機械の躍動感はときに人間を狂暴へと駆り立ててしまいます。
S(Z)MMの音楽はどこかすっとぼけて、括弧付きの「音楽」としては顔をひそめる人もいるでしょう。でも突然叫びたくなっり、スキップしたくなったり、手足に力が湧いてなにがなんでも突進あるのみ!の気分があるじゃないですか。頭で制御できないこのムラ気こそ人間臭い。肉体的な訳の分からない高揚。そこがタマラナイ私のような人間には、トラッド風味や酔っぱらいのような歌い方もひっくるめて、生き生きした「ヴァイタル」な音楽と呼んでしまうのです。
あんまり纏まってないですね、あうー。
2002年9月、ついに来日を果たす。想像以上の躍動感と反射神経、そして「バカ」(笑)。
来日公演の様子はこちら→【Lars
Hollmer来日記念特別ページ】
詳しくはこちら:http://www.amigo.se/krax
:http://www.cabal.se/silence/samla/index.html
(もも)
☆SAMLA MAMMAS MANNA/same (Silence SRS-4604) '71
☆SAMLA MAMMAS MANNA/Ma゜ltid (resouse rescd-505) '73
☆SAMLA MAMMAS MANNA/Klossa Knapitatet (MARQUEE MAR-95119) '74
☆ZAMLA MAMMAZ MANNA/Fo¨r A¨ldre Nybegynnare 〜Schlagerns Mystik
(MARQUEE 9341) '77
☆ZAMLA MAMMAZ MANNA/Familjesprickor (MARQUEE 9342) '80
3枚目と4枚目でSがZに変わっていますが、読み方はどちらも「サムラ・マンマス・マンナ」です。
一般的に入門編は5枚目の「家庭のひび割れ」。Furio Chiricoではないが、メンバー全員の手足が8本あると言われても信じてしまうに違いない。それでいてオッペケペー。わからない人はとりあえず聴く!気に入ったら順に遡って聴いてください。
個人的には2,3枚目を良く聴きます。聴くたびに新しい発見があって飽きません。
☆SAMLA MAMMAS MANNA/Kaka(Amigo
AMCD 884) '99
(Arcangelo ARC-3005) '99
まさかの新作!!!お馴染みTage Asenのしみじみしたアートワークを眺めて感無量。「さすがに老けたなぁ」とメンバーショットを見ながらまず聴いた第一印象は「やっぱり本物は違うぜ!」そして「バカに拍車が掛かってどうする!?」
どうやら通常のスタジオ録音とライブ音源をコラージュして、彼らが実際やっているライブの流れを演出しているようです。
転がるようなイントロから力強いアンサンブルへ、そしてズッコケ。ダンス、民謡、ラウンジと貪欲に吸収しつつ独自のスタイルで表現される一聴してサムラとすぐ分かる音。かといって、いつまでも「家庭のひび割れ」してない、20年近くの歳月と経験を経た新しいサムラがここにありました。
コレクターの間では待望の未収録曲だった"Frestelsens Cafe"と"Ikaren"は三部作構成で収録されてます。待望されていただけあってどちらも佳曲ですし、"Tredje
Ikarien"(Ikarien 第三章、ですね)に至っては感動的。緻密なアレンジの"Satori"もかっこいい。そしてSEのように入ってくるしゃべくりや雄叫びが徹底的に怪しくてタマラナイです。特に11.はオヤヂ達がトチ狂って爽快です。
「出た!」というだけでもう狂喜乱舞ですが、細かいところではThe Flower Kingsでも聴けるHasseのカラフルなパーカッションと久々に聴く鋭いドラミング(このセンスは天才的だ!)、Larsのエレピ弾き倒しが嬉しいです。
☆Samla/Zamla BOX (Arcangelo ARC-3017) '08
Samla/Zamlaのスタジオ盤5枚と、Gregoru Allan FitzPatrickのスタジオ盤2枚を組み合わせたBOXセット。G.A.FitzPatrickの「Bildcircus」は初CD化および「飛び出す絵」完全再現。7作全て紙ジャケ・デジタルリマスター(K2スーパー・コーディング)歌詞対訳付き。Samla/Zamlaのアルバムにはボーナス追加。すげーすげー。Belle
AntiqueからリリースされていたCDとは邦題が変わっているけど、今回の方がより原題に近くなるよう考えられています。とりあえず「ごはんですよ!」最高。
音質について、私は元々無頓着なので、その辺にうるさい人のレビューを探して読んで欲しいですが(^_^;)、「Snorubgarnas
Symfoni」や「Familjesprickor」などは、ドラムに少し重みが増した感じで、より曲の印象が鮮明になったと感じました。 |
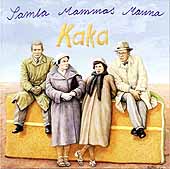
Kaka

Samla/Zamla BOX |

箱の内側は、昔の写真のコラージュ
手前のライオンのイラストは、2枚組が出た後に作られたシングル"Lejonet av Ljuga"のジャケット(絵のみ・音源なし)。資料によると"reggae
protest song"だったそうな。 |

桃屋からちゃんと使用許可を取ったそうです。 |
そして二人が残った。S(Z)MM解体後にHollmerとHaapalaが結成したバンド。
☆VonZamla/Zamlaranamma (MARQUEE MAR-9455) '82
☆VonZamla/No Make Up! (Urspa゜r RSP AR KRAX-3) '83
S(z)MM以後というより、RIO・リコメン系に重心を置くとわかりやすいです。2枚目はMichel Berckmansが参加、と書いてピンと来ない人は聴かなくていいかも(^_^;)。ピンと来た人は一聴の価値あり。当然Univers
Zeroよりカラッとしてます。
☆Von Zamla/1983 (Arcangelo ARC-2121) '99
以前独り言でちらっと書いていたVZのライブですが、なんとCDが出てしまいました。1983年のドイツのBremenとHildesheim2か所の録音から、主に「Zamlaranamma」の曲を収録。明確で親しみやすいメロディーと謎なバッキング、切れのあるリズムが楽しめます。"Haruja¨nta"は哀愁のオーボエとイッてるコーラスを含めて名曲。"Doppler"のループはすでに16年前の人力演奏だけど、今聴いてもクールだ。とにかくS(Z)MMに関わるものがどれか1つでも気に入ってる人は必聴!
ボーナストラックとしてZMM時代の名曲"0¨det"のエディットヴァージョンを収録。
 |
☆Gregoru Allan FitzPatrick/Snorubgarnas Symfoni(MARQUEE
9226) '76
S(Z)MMの4枚目として紹介されることもありますが、実際はG.A.FがS(Z)MMをゲストに迎え録音されたもの。
The Flower Kingsで迷い込んでここまで読んでしまった人、まずはこれでS(Z)MMに触れてみて下さい。北欧特有の爽快感とファンタジー、そしてヴァイタルな音楽の美しくもユーモラスな結晶です。
☆Ramlo¨sa Kva¨llar/Nights Without Frames (resource rescd-507)
'78
S(Z)MMの、テクニカルなところではなく、バックグラウンドが気になる・気に入った、という人向けです。チンドン音楽が好きな人もチェック!スウェーデンのトラッドとオリジナルが半々で、HollmerとApetreaが参加、曲の提供をしています。中古でよく見かけますが(T_T)、時々発作的にとても聴きたくなる作品です。
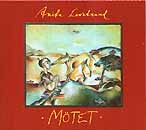 ☆Anita Livstrand / Mo¨tet (MNW RESONANS
MNWCD 3003) '78
☆Anita Livstrand / Mo¨tet (MNW RESONANS
MNWCD 3003) '78
Anita Livstrandなる女性ミュージシャンの作品。タイトルは「ある出会い」ってところでしょうか。S(Z)MMからLars
Hollmer、Coste Apetreaが参加しています。その他Ulf
Wallander、Thomas Mera Gartz、Bengt Bergerの元Arbete & Fritid勢に、KebnekaiseのギタリストKenny Hakanssonとも関連しているTurid
Lundquist等、スウェーデンProgg Rockマニアにはたまらないゲスト陣。この再発盤は1,000枚限定らしいです。
インド音楽にかなり傾倒しているが、極彩色のシヴァ像が似合うギラギラした音楽ではなく、スウェディッシュトラッドと融合した穏やかな音楽になっています。
☆Coste Apetrea / Rites of Passage (Lion Music LMC 167) '06
本来独立したページで紹介できるくらい作品がリリースされているのだけれど、私はCosteの作品は若干枚しか持っていないので・・・。スマヌー
ソロ作品としては1990年にリリースされた「Airborne」以来、16年ぶりのソロアルバム。最近(2007.3月時点)PlanktonやGosta Berlings Sagaを耳にする機会があり、スウェーデンもメロデスとかAORハードばかりじゃなくて、昔からのハードロックが生きてるんだなぁと確認・感心していたところで、70年代からそのシーンで活躍してきたギタリストのアルバムをやっと書ける気になった。前述した若者たちより音が若々しく、スタイルに捕らわれていない感じがする。曲調はヴァラエティに富んでいて、その上でのギタープレイも走るところはマシンガンの如く、ロングトーンは瑞々しく、トブところは遠くへ。しかも優雅だ。Samlaのような素っ頓狂な面はそれほど無いけれど、ギタリストとしての力量を充分堪能できる。個人的にはヘヴィなギターがメインの前半とSaxの穏やかなメロディーから華やかに展開する後半のコントラストが楽しい"Bohumils
Bolero"が好き。全体的にシャリシャリしている音質が気になるのがちょっと残念。
ちなみにLars Hollmerとよく共演しているヴァイオリニスト、Santiago
Jimenezが2曲参加。
詳しくはこちら:
http://www.coste.se/(オフィシャルサイト)
http://www.geocities.jp/coste_apetrea/index.html(日本のファンサイト)

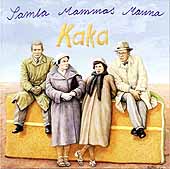



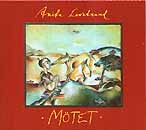 ☆Anita Livstrand / Mo¨tet (MNW RESONANS
MNWCD 3003) '78
☆Anita Livstrand / Mo¨tet (MNW RESONANS
MNWCD 3003) '78