Lars Hollmer
S(Z)MMのメンバーの中ではもっともコンスタントに活動をしてきたのが彼。さらに詳しくは「Andetag」日本盤の本人による年表を読みましょう!すっかりアコーディオン魔人になってますが、もっとピアノも弾いて下さいよう。
2000年12月に初来日を果たしました。
【Lars Hollmer来日記念特別ページ】
☆Vill Du Ho¨ra mer? (Urspa゜r KRAX-1) '82
ソロの2nd。いきなり「イエーィ」だし"Indojazz"なんてインチキ臭い曲はあるし、でもまぁいいか、と許してしまう。ジャケット通りの「おもちゃ箱」サウンド。キーボード類の音色が多彩です。
☆Fra゜n Natt Idag (Urspa゜r KRAX-2) '83
3rd。1曲目の歌い出しこそズッコケてしまうが、全体の演奏は手堅いです。愛らしいメロディーはそのまま、突然の「ドンガラガッシャーン」もほとんどありません。和みます。Hollmerが全パート担当。
☆The Siberian Circus (resouce rescd-502) '93
1980-1988年までに発売されたソロ5作から数曲ずつ収録されたベスト盤。入門用。
☆LOOPING HOME ORCHESTRA/LOOPING HOME ORCHESTRA"LIVE 1992-1993"
(VICTO CD024) '93
LHOバンド名義。タイトル通り集大成的ライブです。元S(Z)MMのLars Krantz(B)、Eino Haapala(G)や、大御所Fred
Frithも参加しています。密室的なスタジオ盤の音に比べかなりダイナミックな音です。人懐っこいメロディ盛り沢山、でもオチョロケは少ないからシリアスなファンもぜひ!
☆XII Sibiriska Cyklar (Resource Rescd 512) '94
Hollmerの初ソロ作品である「XII Sibiriska Cyklar」(1981)と「Vill Du Ho¨ra Mer?」のカップリングCD。Hollmerワールドの原点を確認するにはまずここから。
☆Vandelma¨ssa (AYAA cdt 1093) '94
83年に作られた結構古い曲なども入ってます。S(Z)MM時代からレコーディングに使われていたスタジオ「Chickenhouse」のリニューアルに関するHollmer直筆の文章と、その部屋の様子の写真がインナーに載せられています。自分の父親がこんな部屋にこもっていたらちょっと怖いです。95年にnewヴァージョンが出ているらしいです。聞いてないよぅ(涙)。
☆Andetag (KRAX 10) '97
(Arcangelo ARC-3002) 国内盤 '98
シンフォニック・ロックにも通じるようなアレンジは今までになかったものですが、その根底にあるHollmer節は変わってません。「おいおいっ」と裏手で突っ込みたくなるSEもあれば、思わずホロッとくるメロディーあり。インナーのイラストも素晴らしいです。傑作!
☆Lars Hollmer (resource rescd-517/518) '98
CD化されていなかったソロ3作( 「Fra゜n Natt Idag」「Tono¨ga」LHO名義の「Vendeltid」)をボーナスも含めて2CDにまとめたもの。
| ☆Utsikter (KRAX 11) '00 一聴マニアックな感じがしました。前作「Andetag」に比べるとシンフォ的な派手さが完全に撤退し、今までのソロ作品のようなアコーディオンを中心とした素朴な音、プラスヴァイオリンの華やかな音。曲によってはVon Zamlaを思わせるチェンバーナンバーも。考えるに、Utsikterでツアー活動をしているうちに、ヴァイオリンの使いどころを彼なりに消化した上で現れた変化だと思われます。 とはいえ、どこを切ってもいつものホンワカHollmer節。シリアスすぎず、オチャラケ少し。今作は特に美しいメロディーを生かすために、周りの音を選びに選んだ感じがします。 「Andetag」までの可愛い音楽、変な音楽、泣ける音楽、よく分かんない音楽を通過してきて、自分の音楽への視野がかなりはっきりしてきた、あるいは新たなステージを迎えたと言うところでしょうか。ジャケットによく使われていた「窓」から、外へ。 そういえばutsikerの意味は「views」だそうです。 |
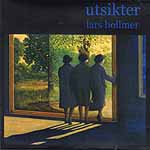 Utsikter |
| ☆Autokomp A(nd) More (KRAX 12)
'01 2001年来日記念盤。80年代のソロ曲の未発バージョン、別ミックス、未発曲などが収録されもの。なので最近のシリアス路線ではなく、いわゆる「おもちゃ箱をひっくり返した」ような音です。息子さんとのデュエットもなかなか微笑ましい。 このCDは来日公演を行ったTLGとStar Pines Cafeの両会場のみでの発売されました。500枚限定生産。(Hollmer直筆ナンバリング入り)ジャケはHollmerの愛娘Rindaさんのイラスト。味あり過ぎ。 (でも柏のユニオンで売ってるのを目撃。) ☆SOLA Lars Hollmer's Global Home Project (Krax 12+1 / Tutinoko TUTI-0002) '02 シットリと聴かせる最近のHollmerのソロの中では、かなり異色のアルバムではないだろうか。その原因は吉田達也のドライブ感溢れるドラミングにあり。ロックしているのだ。ストレートな音に、去年の来日公演と曲目がほぼ重なっているので、コレを聴いて来日公演のデジャ・ヴに包まれる人もいるだろう。アカデミック臭さを感じさせないニートな演奏(個人的にはこの辺りが日本的かと)に、百戦錬磨のミュージシャン達の実力を感じる。中でも向島のヴァイオリンはHollmerの曲と相性が最高!すでに何度か録音されている曲も多いにも関わらず、味わいがにじみ出てくるのは楽曲の力ですね。 バンドを自主練習地獄に陥れた(笑)因縁の曲"Parallell Angostura"はLHOでは荘厳な印象だったが、このアルバムのヴァージョンは不思議な浮遊感があって、また違う印象の曲に仕上がった。一部RUINS化はリベンジ完了の印か(笑)。 "Yrsa Requem"は去年亡くなった愛犬に捧げる鎮魂歌。ボーナストラックは2000年来日公演で演奏された"Hoppas Att Det Ga゜r "。 ☆Lars Hollmer Yuriko Mukoujima Duo Live and More (Krax 15 / Tutinoko TUTI-00026 '03 2003年3月のライブが好評で、同年の10月には北海道と東京で公演が行われたHollmerと向島の最強ほのぼのタッグ。2人の相性の良さはすでにライブでも証明済みですね。 このアルバムは3月のライブと"Tama-chan Snoa"、"Wave to C"新曲2曲を含む変則ミニアルバムで、ジャケットの絵はお馴染みとなったRinda嬢の力作です。ライブに来なかった人はこのアルバムを聴いて雰囲気を味わってくださいね。愛だろ、愛。 |
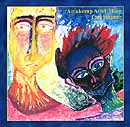 Autokomp A(nd) More  SOLA |
| ☆Panta Rei / same (Asid Symposium AS009) '73 ジャケのインパクトが強烈なので、聴かず嫌いされている方が多いと思われるPanta Rei唯一のアルバム。内容はまっとうなので、恥ずかしがらずにレジに向かって欲しい(^_^;)。 Lars Hollmerが一曲目"Five Steps"の作曲に関わっているが、演奏はしていない。ファンキーなブルーズロックで、Thomas Arnesenの伸びやかなギターソロが気持ちよい。ThomasはCoste Aptreaが加入する以前にSamlaのメンバーだったことがあるらしい。他の曲もブルーズを基調にした少しサイケがかった雰囲気。スウェーデンの、のどかというか、たおやかな空気感が好きな人には気に入ってもらえるだろう。歌詞も英語で歌われているので取っつきやすいと思う。 ブックレットなどでは全5曲と表記されているが、CDプレイヤーの表示は6曲。5曲目の"The Knight"が13:45の長さがあるのだが、2曲に分けられてしまっている。 ☆Fem So¨ker En Skatt (KRAX 9) '95 演ってることは、S(Z)MMの項で紹介した「Ramlo¨sa Kva¨llar」に近いのですが(メンバーも殆ど一緒)、音がもっと軽めです。裏ジャケットにはダンスするカップルがいるライブハウスの写真が使われていますし、眉間にしわを寄せて作ったものではないことは明らかです。半分はライブ録音。Hollmer、裸足です。SaxにThe Flower Kings等にゲスト参加しているUlf Wallander。 |
 Panta Rei |
| ☆Volapu¨k / Polyglo¨t (Cuniform Records RUNE
134) '00 フランスのチェンバーロックトリオ。Hollmerは"Voila Pu¨k"という曲(「Utsikter」にも収録)を提供、自らアコーディオンやメロディカを演奏している。バンドは違えどHollmer節。でもこのバンドの雰囲気にとても合ってると思う。 暗黒Cro Magnon・アジアン風味?と思ったら、After Dinnerのヴァイオリニスト福島匠がゲストで参加していた。暗黒といってもサラッと聴けるところがフランスかな。良いです。 ☆Miriodor / Parade + Live at NEARfest (Cuniform Records RUNE 208/209) '05 カナダのフランス語圏ケベック州のベテラン・チェンバーバンド。Hollmer氏は"Talrika"、"Bonsai Givre"、"Foret Dense"の3曲に参加している。"Talrika"はHollmer氏のオリジナル曲。チェンバーロックファンには安心してお薦めできるクォリティだが、Hollmer氏のトラッドサウンドを求めると少し期待外すかも。しかし「この曲で弾いてるだろ?」と一聴して分かる独特のアコーディオン(特に低音部)は健在。 ボーナスディスクは2002年に出演したNEARfestでのライブ音源。当日演奏された13曲丸々収録されている。無機質、かつ、おどろ可愛いサウンドがタイトな演奏で繰り広げられている。このライブは楽しそうだな。 詳しくはこちら。 |
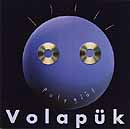 Volapu¨k / Polyglo¨t |